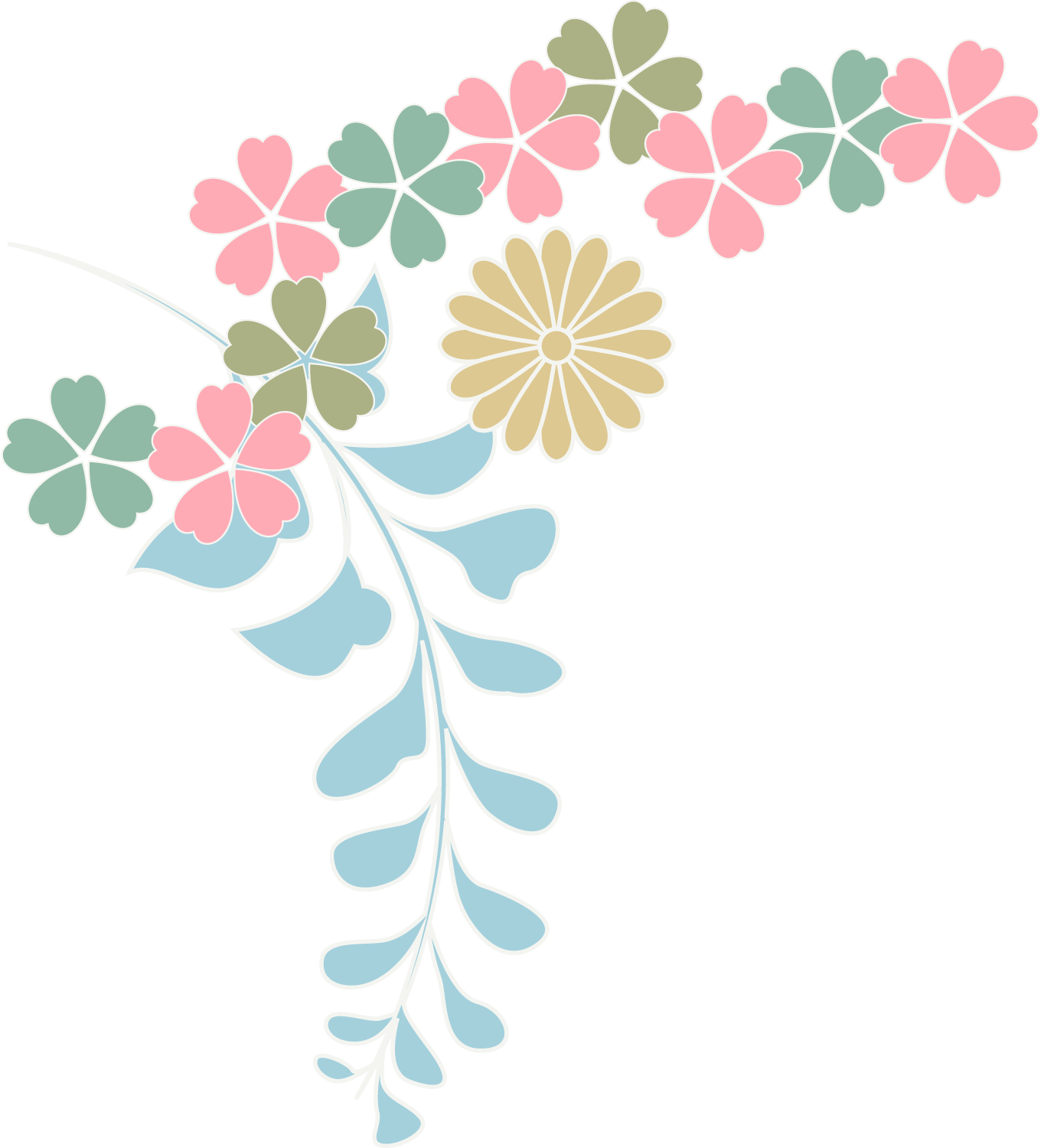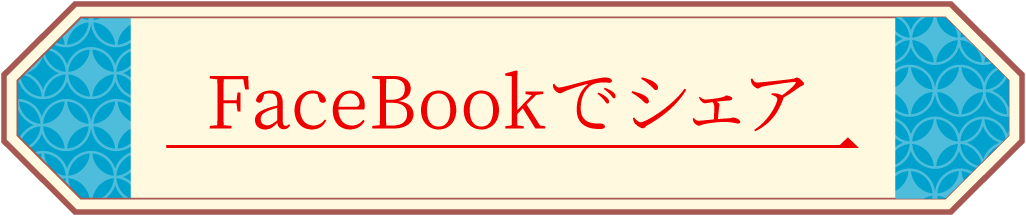===============================================================================
『倉吉八犬伝』ショートショート
旧国鉄倉吉線廃線跡 篇
登場人物:犬江嶺仁朗/犬田悌寛
===============================================================================
<犬江嶺仁朗視点>
妖女・玉梓の呪いによって、悪さをしているあやかしなどはいないか。
八犬士の面々で話し合った結果、俺たちは四手に分かれて倉吉市内を時々巡回する事になった。その日は俺と悌寛で、関金にある旧国鉄倉吉線廃線跡までやってきた。
「少し奥まったところにあるんだな。静かで落ち着きいた、趣きのある素敵な場所だ」
その景色に目を細めていると、悌寛が俺の横にやってきた。
「れいくんと一緒にお出かけなんて、久しぶりだよね! 嬉しいなあ。あ、ここ蚊が多いから虫除けしておかないとね。そこは段差があるから危ないよ、気をつけて! ああ! そんなに腕を出したらケガしちゃうから……」
「しつこいぞ、悌寛! 俺はもう幼子じゃないんだ。あれこれ気にかけてくれるな。あと、“れいくん”はやめてくれ」
「でも、やっぱり甥っ子は可愛がりたいというか……」
「結構だ、伯父さん!」
フン、と鼻を鳴らして悌寛を置いていく。すると後ろから、悌寛が慌てて走ってきた。
悌寛は誰に対しても優しいが、甥に当たる俺に対しては顕著で、猫可愛がりする傾向がある。幼子の頃、悌寛が面倒を見てくれたからだと思うが……それにしても、気にかけすぎだ。俺はもういい年をした大人。いつまでも子どもではないのだ。
「待ってよ、れいく……嶺仁朗くん」
やっと呼び方が戻ったが、立ち止まる義理はない。そのまま放って、線路の上を歩いていく。そもそも悌寛は背が高いので、少し早歩きすれば……ほら、もう追いついてきた。
「この線路の上を、昔、『でんしゃ』ってやつが走ってたのか」
ここへ来る前、旧国鉄倉吉線廃線跡について伯姫の数珠を持つ彼女が教えてくれたので、ある程度は知っていた。だが、実際にこの目で見るのは全然違う。俺たちはこの線路よりも更に昔に生きていたというのに、なんだか感慨深くなる……不思議だ。
悌寛は、『ほーむ』と呼ばれる、石のようなもので出来た場所の上に設置された看板を見ていた。そこには、『泰久寺』と書かれており、場所を示しているのだという事がわかる。
「昔は、ここにいろんな人が立っていて、『でんしゃ』を待っていたり、乗り込んだりしていたんだろうね」
「俺たちが生きていた時代よりは、近代だろう。それより、先へ行こう」
「うん」
木と鉄で出来た線路の上を、悌寛と並んで歩く。そんな俺たちの両脇には、竹林が広がっていた。
「うわぁ……! すごいね! 左手は斜面になっていて……竹、竹、竹だ」
「右手も、こちらに迫ってくるように竹が伸びているな」
人の手が入らなくなったからだろう。竹はすくすくと成長していき、空を覆い尽くさんばかりだ。その隙間を、太陽の光が入り込んでいる光景が、なんとも言えず幻想的である。
まるで妖術にかかったかのように思えるが……ここはまぎれもなく現実で、今見ている光景も本物だ。俺は首を横に振り、先を歩いていく。
「あ、ここは橋になってるんだね。下は川なのかな?」
悌寛は橋の限界まで立ち、下を覗き込もうとする。
「おい、そんなに覗き込んでいると落ちるぞ。いくら力自慢の君でも、こんなところから落ちたらひとたまりもないんだ」
身体を起こした悌寛は、目を丸くしてこちらを見た。
「れいくん、気遣ってくれるんだね……!」
「別にそういう意味じゃ……というか、また呼び方が戻っているぞ」
「あ……あはははは。つい……ごめんね。でもほら、今は俺たちふたりだけなんだし、そんなに気にしなくても……」
「俺が嫌なんだ」
わかっているのか、いないのか。悌寛は申し訳なさそうに笑ってまた歩き出した。いい加減伯父面をするのはやめてほしい。
「それで? 川は流れていたのか?」
「全然だったよ。川じゃなかったのかな?」
「もしくは、細い川だったのが枯渇してしまったのかもしれないな」
「じゃあ、なくなったのは『でんしゃ』だけじゃないって事か。そう考えると、ちょっと寂しくなるね……なんだか嶺仁朗くんみたい」
意味がわからなくて、立ち止まってしまった。そんな俺を見て、悌寛は困ったような、泣きそうな、なんとも言えない表情で笑う。
「幼い頃は、にーたんにーたんっていっつも俺にくっついてきて、寝る時だっていつも一緒だったのに……今じゃつれないし、全然可愛がらせてくれないんだもん。寂しいなあ」
「それとこれは話が違うだろ」
「同じだよ。あの頃はもう戻ってこないっていう切なさがこう……」
「俺はただ成長したで、何も変わっていない。というかいい加減幼い頃の話はやめろ!」
とうとう声を上げてしまった。それでも悌寛は「可愛かったのになあ」と寂しそうにする。そんな顔をされると、まるで俺が悪いみたいじゃないか。腹立たしくて、悌寛を置いて先へ行く。
「あ! 待ってよ、嶺仁朗くん!」
「大人になって可愛げのない俺の事は放っておけばいいだろう」
「可愛げないとか言ってないよ? 今も可愛い……」
「可愛くはないだろう!」
悌寛といると疲れるな……。
ため息をつきながら歩いていくと、とうとう行き止まりまで来てしまった。
「ここは……『とんねる』というやつか」
「鉄の扉で塞がっているみたいだね。これ以上先には行けないみたいだ」
すぐに追いついた悌寛が、横に並ぶ。
「だが、本来はこの先にも線路が続き、『でんしゃ』が走っていたんだな」
「そうだね……」
その時だった。
タタタン、タタタン
小気味良い音が、背後から聞こえてきた。
「っ!?」
まさか玉梓の呪いか?
慌てて振り返った……次の瞬間。
俺たちの身体は、乗った事もない『でんしゃ』の中にあった。
「この先に、俺たちを連れて行ってくれるのか?」
タタタン、タタタン
俺たちを乗せた『でんしゃ』は車体を揺らしながら、『とんねる』を抜け、田畑の間を縫うように走り、山へ向かっていく。
更に木々を抜け、空を抜け、更に先へ――。
「ここは……殿様のお屋敷……?」
窓の向こうに見える懐かしい姿に、俺たちは慌てて駆け寄った。間違うはずがない。それは俺たちの主である里見の殿様が住まわれていた、関金の屋敷があった。
電車が止まると、扉が開き……下りてみると、目の前には殿様と伯姫が並んで立っていた。まるで、俺たちを待っていたように微笑むふたり。
「伯姫、ここにいらしたのですね」
「姫……!」
思わず手を伸ばした……けれど、掴んだのは、ただの空気。
「っ、あ……俺は……?」
殿様も、伯姫も、屋敷も、どこにもなかった。俺はいつの間にか、幻を見ていたのだ。
「あはは……俺、幻を見てたみたい」
「悌寛もか」
「嶺仁朗くんも?」
ふたりで同じ幻を見るなんて、ありえるのだろうか。
顔を見合わせるが……答えが出る事ではない。悌寛は首を横に振って、いつもの柔らかな笑みを浮かべた。
「帰ろうか」
「……ああ。そうだな。玉梓の呪いはなかった」
「うん、そうだね」
来た道を戻って行くが……俺は途中で立ち止まり、振り返った。
そこにあるのは、その昔は大きな口を開け、様々な人を運ぶ『でんしゃ』を通していた場所。その役目を果たし、静かに眠る『とんねる』
「……君が見せた夢だったのか? それとも……」
「嶺仁朗くん、早くしないと暗くなっちゃうよー」
「……ふっ。まあ、いいか」
「嶺仁朗くーん?」
「今行く」
今度こそ背を向けると、俺は悌寛の方へ向かって歩き出した。
◆END
著:浅生柚子(有限会社エルスウェア)



「旧国鉄倉吉線廃線跡」